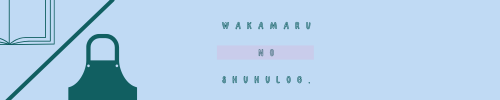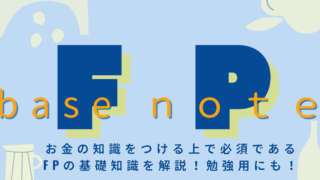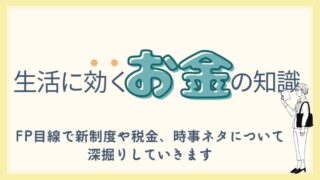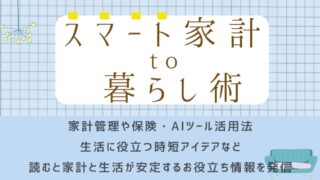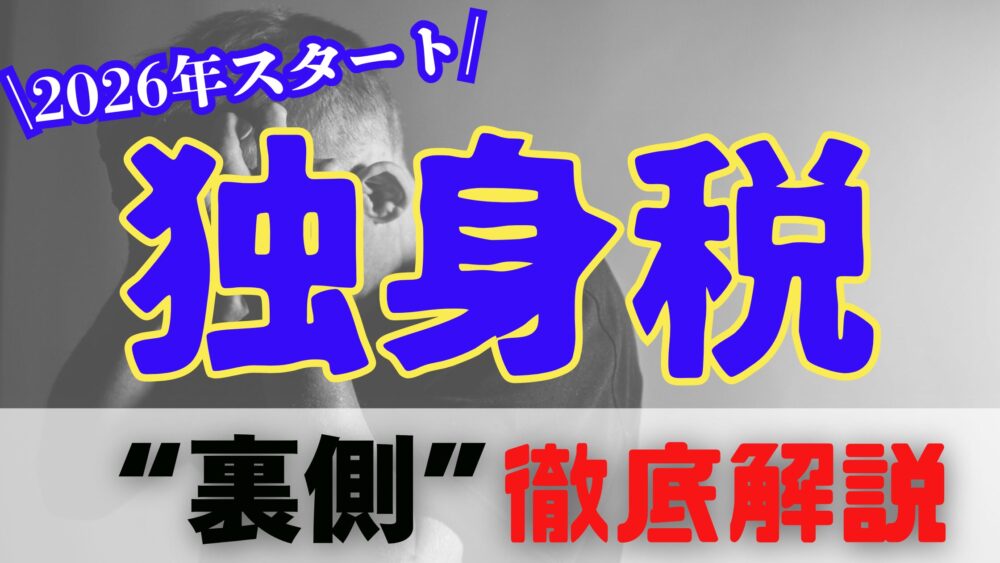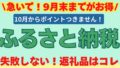2026年4月から新たに導入される「こども子育て支援金」制度。
この制度が今、「実質的な独身税では?」とSNSやネット掲示板などで大きな話題になっています。
表向きは“子育て支援”の制度ですが、その仕組みをよく見ると、独身者を中心とした現役世代の負担が増える仕組みになっているのです。
本記事では、この制度の「仕組み」と「裏側」、そして本当の“もくろみ”まで、わかりやすく整理します。
「独身税」はいつからスタート?──制度の概要と導入時期
正式名称は「こども子育て支援金制度」。
スタートは2026年4月。
社会保険料(健康保険料や国民健康保険料)に上乗せされる形で徴収されるため、給与明細上は「保険料増加」として現れます。
- 初年度:月250円程度
- 数年後:月450円へ段階的に引き上げ予定
▶ 年間で5,000〜6,000円規模の“実質的な増税”
なぜ「独身税」と言われるのか?──制度の構造が生む違和感

この制度は、すべての健康保険加入者が対象で、独身でも既婚でも、子どもがいてもいなくても、一律で負担が発生します。
しかし、集められた支援金の恩恵を受けられるのは基本的に子育て中の家庭のみ。
そのため、独身者や子どもがいない家庭にとっては「払うだけ」の制度となってしまいます。
この一方通行の構造が、「独身税」と揶揄される最大の理由です。
集められた支援金の使い道は「こども未来戦略」
政府は、集められた支援金を「少子化対策のための安定財源」と位置づけています。
具体的には「こども未来戦略」を推進するために使われ、以下の5つの柱が掲げられています。

1. 児童手当の抜本的拡充
以前からあった児童手当ですが、2024年10月に制度の抜本的な拡充が行われています。
▶所得制限の撤廃
▶支給年齢の延長
中学卒業まで→高校卒業まで
▶第3子以降の増額
月1.5万円→月3万円支給
▶支払い月の変更
3回/年→6回/年(偶数月)
【支給額一覧】
| 対象の子ども | 支給月額(全世帯対象) |
|---|---|
| 0歳〜2歳 | 15,000円 |
| 3歳〜高校卒業まで (第1・第2子) | 10,000円 |
| 3歳〜高校卒業まで (第3子以降) | 30,000円(全年齢) |
2. 保育サービスの拡充と質の向上
▶こども誰でも通園制度の創設
親の就労要件に関係なく保育所利用が可能に
▶保育士配置基準の改善
手厚い保育を実現
▶学童保育の待機児童解消
これは、まだまだ実現されてないですね。これからに期待。
3. 育児休業給付の充実
父母ともに育児休業を取りやすくなる給付制度への見直し(2025年4月から導入)
4. 妊産婦への支援強化
▶妊娠・出産費用の保険適用
▶相談支援の強化(伴走型支援)
これもこれからでしょうか?
現在は出産一時金50万円がそのまま病院へ流れる形になっていますが、帝王切開などの場合には追加の費用が必要。
5. ひとり親家庭や障害児家庭への支援拡充
困難を抱える家庭に対し、きめ細やかな経済的・福祉的サポートを実施
実態データで見る:「独身者」はどれくらいいるの?

「独身税」が話題になるのは、独身者の割合が無視できないほどに増えているからです。
年齢別の未婚率は?(2020年 国勢調査)
| 年齢層 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 25~29歳 | 76.4% | 65.8% |
| 30~34歳 | 51.8% | 38.5% |
| 40~44歳 | 32.5% | 21.6% |
| 50歳時点 | 28.25% | 17.81% |
→ 男性の約4人に1人、女性の約6人に1人が50歳までに結婚しない「生涯未婚」の時代。
世帯構成から見る『子育て世帯』の割合は?(2020年 国勢調査)
| 世帯の種類 | 割合 | 解説 |
|---|---|---|
| 単独世帯 (独身に近い) | 38.1% | 最も多い世帯構成。 |
| 夫婦のみ (子なし) | 20.1% | 高齢夫婦などが中心。 |
| 夫婦+子ども | 25.1% | 『独身税』の恩恵を受ける世帯層。 |
▶ 今や日本の標準は「独身世帯」。
にもかかわらず、制度設計では「子育て家庭」を中心に支援が偏っている現状がみえます。
『独身税』導入前‟現在”の『子育て支援策』の財源はどうなっている?
結論から言うと、現在の財源は非常に複雑で、制度ごとにバラバラの場所から集められています。これが、政府が「安定した一元的な財源が必要だ」と主張する理由の一つになっている。
主な支援策ごとに、現在の財源は以下のようになっています。
1. 児童手当の財源
主に国、都道府県、市区町村が分担して税金から支出。その分担割合は以下は、
- 国: 約3分の2
- 都道府県: 約6分の1
- 市区町村: 約6分の1
2. 保育サービス(保育所の運営など)の財源
保育所の運営費などの財源は、さらに複雑で、以下の3つで構成されています。
- 公費(税金):約50%
国・都道府県・市区町村からの税金。 - 保護者が支払う保育料:約10%
世帯の所得に応じて、保護者が直接支払う保育料。
(※2019年10月から3~5歳児などは無償化されました) - 企業が支払う社会保険料(子ども・子育て拠出金):約40%
これが少し特殊で、現在の「支援金」制度の元になった考え方です。
従業員の給与からは天引きされず、企業(事業主)のみが負担している社会保険料の一種で、「子ども・子育て拠出金」というもの。
すべての企業が、年金保険料などと一緒に国に納めており、これが保育所の運営費などに充てられています。
3. 育児休業給付の財源
育児休業中に支給される「育児休業給付金」は、上記の2つとは全く財源が異なります。
▶労働者と企業が支払っている「雇用保険料」から出ています。
現在の主な財源:まとめ表
| 制度 | 現在の主な財源 |
| 児童手当 | 国・都道府県・市区町村の税金 |
| 保育サービス | ① 国・都道府県・市区町村の税金 ② 保護者の保育料 ③ 企業の社会保険料 (子ども・子育て拠出金) |
| 育児休業給付 | 労働者と企業が支払う雇用保険料 |
なぜ新しい「支援金」が必要なのか?ー政府の主張
ご覧のように、現在の子育て財源は、税金、個人の負担、企業の社会保険料、雇用保険料と、様々な場所に分散しています。
政府の主張は、
「これでは景気によって税収が変動すると財源が不安定になる」
「社会全体で支えるという理念が分かりにくい」
といった課題があるため、医療や年金のように社会保険の仕組みの中に、安定した子育て支援の財源を新たに作りたい、というものです。
そして、その新しい財源として、これまで企業だけが負担していた「子ども・子育て拠出金」の仕組みを、個人(被保険者)にも広げたのが「子ども・子育て支援金」である、と位置づけです。
景気さえ回復すれば、すべて解決するのですが…
制度の「裏側」にある4つの懸念点

① 実質的な“ステルス増税”
政府は「増税ではない」と説明しますが、保険料という名目で自動的に徴収され、給与から天引きされる仕組み。
実態は、『言葉を変えた増税”』との批判が噴出しています。
② 給与は増えず、負担だけ増える?
岸田首相は「実質的な負担は生じない」と説明しましたが…
▶賃上げは企業努力に依存
▶歳出改革の効果は不透明
手取りは実際に減るため、政府説明との乖離が問題視されています。
③ 現役・独身世代への負担集中
▶子育て支援の恩恵を受けるのは一部
▶すべての保険加入者に等しく課される
若年層・非正規労働者・独身者など、すでに経済的に厳しい層にさらなる負担が集中してしまう…
④本当に少子化対策になるのか?
出生率の低下要因は「未婚化・晩婚化」にあります。
▶結婚した夫婦の出生率は約1.9人と安定
▶問題は“そもそも結婚しない人”の増加
結婚・出産を促すには、独身層への「支援」こそが必要なのでは?
政府の“もくろみ”とは?

1. 安定した財源を確保したい
▶税収に頼らず、保険料で恒常的な財源を確保
▶少子化対策は一時的ではなく、持続可能な制度が必要
2. 「増税」と言わずに国民負担を増やしたい
▶増税という言葉を避けたい政権
▶支援金・保険料という形にして政治的リスクを回避
3. 社会全体で子育てを支える「全世代型社会保障」
▶医療・年金に続き、子育ても社会保険化したい
▶子育てを「個人の責任」から「社会全体の責任」へ転換
コラム:「独身税」は本当に悪?世間の不満『真の原因』とは?

「子ども・子育て支援金」によって独身者や子どもを持たない家庭にも一定の負担が課されることから、「独身税」と揶揄されているこの制度。でも私は、この仕組みが必ずしも悪いとは思っていません。
たとえば、災害時に集められる復興支援税のように、「自分には直接のメリットがないけれど、社会全体のために必要なお金」ってありますよね。今回の支援金も、それに近い存在なのかもしれません。
確かに、現代の日本は子育てしにくい社会であり、子どもを持つことに対する“旨味”があまり感じられないのが現実。そんな中で、子育て世代をもっと支援する仕組みを作ろうという動き自体は、将来を見据えた上で必要な施策だと感じます。
一方で、「独身税」という言葉がここまで広がってしまった背景には、やはり政府に対する根強い不信感があるのではないでしょうか。
「本当にちゃんと子育て支援に使われるのか?」「また官僚や政治家の都合のいいように使われるのでは?」という不安。
その不透明さが、「納得できない」「自分たちばかり損をしている」という感情につながりやすくなっているのだと思います。
また、今の日本では「結婚したくてもできない」人も多くいます。
低所得や過密な労働環境のなかで、結婚や子育てどころか、自分自身の生活で精一杯。そんな状況で「結婚しない人からも取る」と言われれば、やはり理不尽さを感じざるを得ません。
だからこそ、もし国が本気で少子化対策を進めるつもりなら、「子育て世代を支える」だけでなく、「独身世代がもう少し余裕を持って生きられる社会にする」ための施策にも、同時に取り組んでほしいと願います。
将来の日本のために、みんなで少しずつ支え合う。
その理念自体は素晴らしいと思うからこそ、政府には誠実な運用と、納得のいく説明、そして幅広い世代を支える公平な制度設計を求めたいですね。