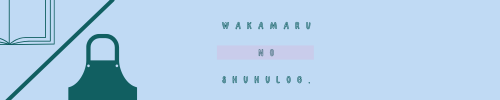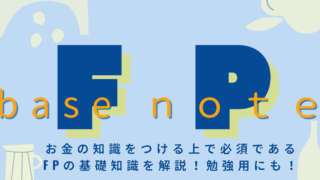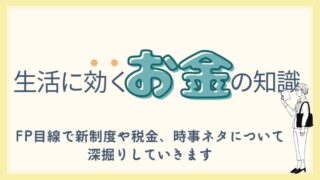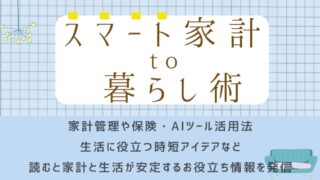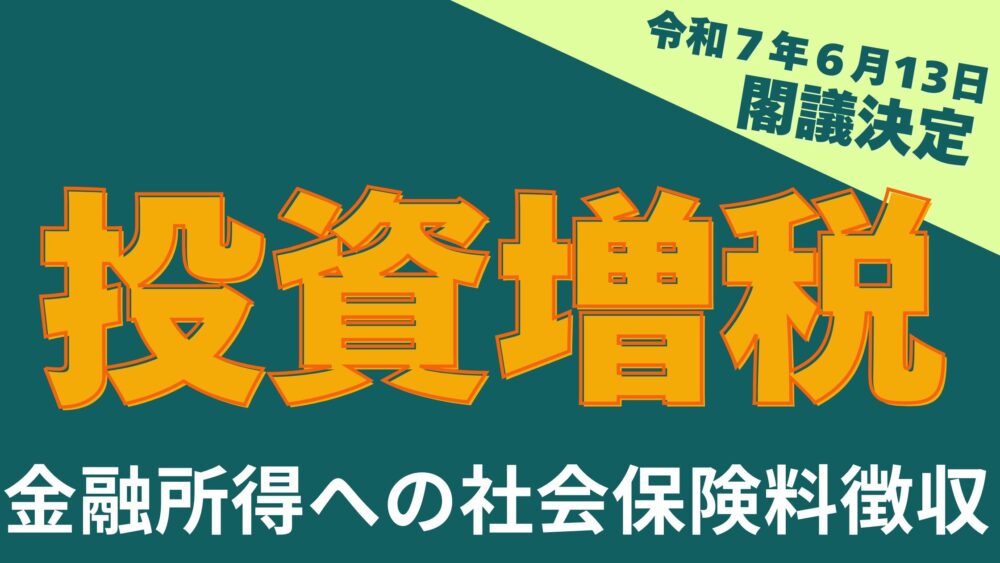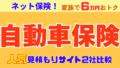こんにちは!わかまるです。
最近、「NISA始めました!」なんて話、よく聞くようになりましたよね。「うちもちょっとだけ株やってみようかな」「iDeCoも気になるなぁ」なんて考えているあなた、今ちょっと気になる話が浮上しているのをご存じですか?
それは…「投資で得た利益にも、社会保険料がかかるかもしれない」というニュース。え?それってどういうこと?せっかくお金を増やそうとがんばってるのに、保険料まで取られちゃうの?と不安になるかもしれません。
でもご安心を!この記事では、その背景とポイント、私たちにできる対策まで、分かりやすくお伝えしていきます。
「えっ、これ友達にも教えなきゃ!」と思える内容になっているはずなので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね
2028年「投資で利益が出たら、保険料もね」そんな未来が来る?

まず、今まではこうでした↓
- 株の売却益や配当金
所得税・住民税はかかるけど、社会保険料は対象外 - 給与所得(働いたお給料)
税金も、社会保険料もしっかり引かれる
つまり、働いて得たお金にはしっかり保険料がかかるのに、投資の利益にはかからなかったんです。
でも、これに対して「不公平じゃない?」という声があがってきたのが、今回の議論のきっかけ。
そこで政府は、2025年の「骨太の方針(経済財政の基本方針)」の中で「金融所得も社会保険料の計算に反映させる方向で検討する」と発表しました。
実施は早ければ2028年度になる可能性もあるとのこと。
静か〜に始まっているこの動き、ちょっと注目しておいた方がよさそうです。
「金融所得にも保険料を」投資増税が公平性の確保?
実は、今回問題になっている「金融所得に社会保険料をかけるかどうか」の議論で、いちばんのポイントはここです。
自営業やフリーランスは確定申告で金融所得も保険料対象となり、すでに投資利益に保険料を払っています。一方、会社員は給料から保険料が引かれますが、投資利益にはかかっていません。
「会社員+投資家」が優遇されていると指摘があり、公平性確保のために保険料かけようぜってことになったようです。
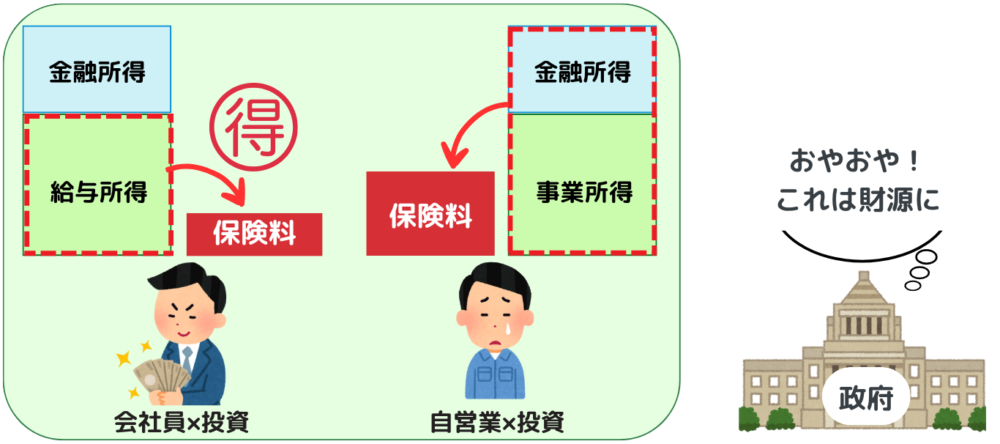
◆【自営業・フリーランス×投資家】
確定申告で「金融所得」も保険料の対象→ すでに投資利益にも保険料がかかっている
◆【会社員×投資家】
給与には保険料がかかるけど、投資利益にはかからない→ ここが“抜け道”になっている、と指摘された
※自営業者が一般口座、会社員が特定口座の場合。
実際には、社会保障制度の維持のための新しい財源がほしい→「あ!見っけた」というのが政府の本音では…
「貯蓄から投資へ」「NISAを使おう」と言ったのに…矛盾してない?
ここでちょっとモヤっとするのが、政府はここ数年、「投資しよう!NISA使おう!」ってずっと推してきたという事実。
- NISAの非課税枠が拡大
- iDeCoの使いやすさUP
- 「貯蓄から投資へ」がスローガン
…なのに、いざ利益が出ると「保険料も払ってね」なんて、まるでアクセルを踏みながらブレーキを踏むような話ですよね。
実際、専門家の間でも「これじゃあ投資する人が減ってしまうのでは?」という懸念が出ているようです。
【2025年】もう始まっていた!富裕層向けの増税(金融ミニマム課税)
ちなみに、2025年1月からは「金融ミニマム課税」という新しい制度がすでにスタートしているんです。
これは、
- 年間所得が3.3億円以上の人には
- 金融所得も含めて実効税率30%以上にしますよ(従来:一律 約20.315%)
という超富裕層向けの課税。
「いや、うち関係ないし」と思ったあなた。
実はこの制度、将来的に対象が広がる可能性が指摘されています。
つまり、「超お金持ちだけ」だったはずが、
1億円前後の人➡数千万円の人➡私たち中間層まで…?
となっていくリスクがゼロではないんです。
NISAで得た利益は保険料の対象?
NISAせっかく始めたのに!という方。安心してください。
現時点では、NISAで得た利益は保険料の対象にならないと考えられています。
なぜならNISAは「非課税制度」=そもそも所得として扱わないから。
ただし、「制度っていつ変わるかわからない」
というのも事実なので、完全に安心とは言い切れません。しっかり政治を見ておきましょう!
私たちにできる「お金を守る5つの対策」
それじゃあ、将来に向けて何ができるの?
ということで、今からできる対策を5つまとめてみました。
① NISA・iDeCoの枠内で投資する
非課税の“安全地帯”を活用!
NISAやiDeCoは今のところ課税も保険料も対象外です。
(※ただし今後制度が変わる可能性はあるので、最新情報をチェックしよう)
② 短期売買は控えめに
売るたびに利益=所得が出るので、買ったら長く持つ「バイアンドホールド」戦略が◎。
③ 確定申告不要口座を使う
証券会社の「源泉徴収あり特定口座」なら、基本的に申告不要=金融所得を“表に出しにくい”形に。
今のところ、特定口座(源泉徴収あり)で投資していれば、たとえ利益が出ても保険料に影響しないのが現実。
でも将来的には、マイナンバー連携でそうはいかなくなるかも…?なんてウワサも。
④ 法人や退職金制度の活用
ちょっと高度な話ですが、企業型DCや法人設立による資産分散も選択肢に。FPや税理士に相談してみるといいかも。
⑤ 情報を「知って」「伝えて」「投票する」
私たちができる最大の行動は「知ること」。
そして、「これってどうなの?」と声に出すこと。選挙も立派な意思表示です。
まとめ:お金を守るには、まず“知る”ことから
今回の話は、まだ決まった制度ではありません。でも、「いつの間にか決まってた」「知らないうちに損してた」では、悔しすぎますよね。
投資はあくまで、将来の安心やゆとりのためにするもの。そこに不安が混じってしまっては、本末転倒です。
だからこそ、「ちょっと気になるな…」と思った今がチャンス!
- NISAは大丈夫?
- どこからが対象?
- どうやって備える?
このあたりを家計の作戦会議ネタとして、家族としっかり話してシェアしてみてください。
あなたの「知ってる」が、誰かの未来を守る力になるかもしれません。
家計を守るのは、知識と小さな行動の積み重ね
一緒に、変化の波にのまれず、賢く楽しく生き抜いていきましょう!